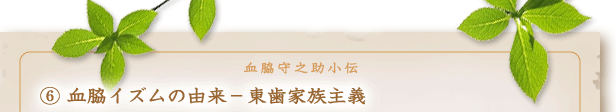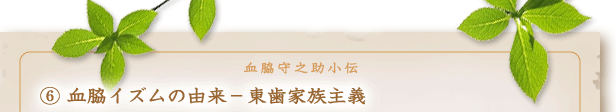野口清作(英世)が守之助を頼って会津から上京し,学院に転がりこんだのが明治29年11月,その友人となった石塚三郎も受付・会計係として学院の学僕を務めていた。当時20代の守之助の,野口に対する援助には敬服させられる。高山院長に交渉して4円の月給を7円にしてもらい,そのなかからドイツ語の月謝1円を含めて2円を野口に渡しているが,守之助は野口に“君のおかげで昇給したよ”と告げたという。また,後期試験(実地)に臨んで済生学舎に入学したいという野口のために,院長に医院の経営を任せてもらうよう交渉し,学費と本郷の下宿代15円を捻出している。
このような守之助の親分肌の気性は,盲目的な心情によるものではなかった。野口に対する寛容を非難する声に対し,守之助は“人それぞれに,おのずから異なった天分がある。いかなる潮流に処しても,学徒の本分を守ってよく学ぶ者には非難すべき理由がない。野口は希代の天才児で,これを型にはめすぎて律することは,彼の天分を大成させる所以ではない。これに対し小林の場合は遊興に耽って学業を疎かにしている。まして天才に比すべき何物もない常人である”と喝破したという。
小林とは信州飯田出身の織物屋の息子・小林太郎で,品川の遊里に足を踏み入れて放蕩を続け,守之助の逆鱗に触れた。寄宿舎を追いだされた小林は,改心して勉学に励んでいたが,急性腹膜炎で入院した。このとき守之助はいったん叱りつけた小林を見捨てず見舞にかけつけた。激励に訪れた石塚三郎に,小林は最後の願いとして,血脇先生から受けた恩義を自分に代わって返すよう頼んだという。守之助は葬送の準備を整えて院長・高山の列席を願ったが,門下の葬儀には参列できないという院長夫人の言葉に落胆した。守之助にしてみれば,学院の学生,教員は同じ屋根の下で暮らす家族であった。
後年,守之助は東京歯科医学専門学校の使丁“熊さん”(島根熊吉)の死に際して盛大な学校葬を行って家族主義を実践したが,この東歯家族主義は,守之助が小林太郎の葬儀でなめた苦渋から生まれたものであり,血脇イズムを構成する太い柱となっている。
|
|
|