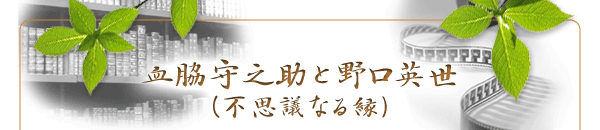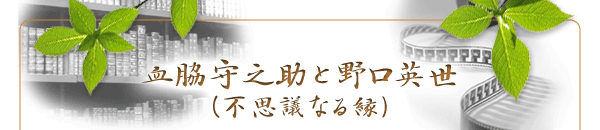|
野口清作(後の英世)は、明治9年(1876)11月9日、福島県耶麻郡猪苗代町の農家に生まれた。2歳の時に囲炉裏に落ちて左手に火傷を負った話はあまりにも有名である。左手はすりこぎ状に癒着し、心ない子供達は“手んぼう”とあだ名をつけた。しかし、彼はそうした身体的ハンディをばねにして、強靱な肉体と集中力を養って小学校でも抜群の成績を収め、猪苗代高等小学校の主席訓導であった小林 栄に認められた野口は、猪苗代高等小学校でも、4年間、常に主席を通
した。
明治25年秋、清作は癒着した指を切り離すため、会津若松の会陽医院で、アメリカ帰りの外科医・渡部 鼎の執刀による手術を受ける。手術は当時の外科手術の水準から言えば成功であり、この頃から、清作は漠然と医師になる希望を抱いた。しかし、医師になるには手先の器用さが必要であり、医科大学を卒業しなければならず、それ以外の方法としては、医術開業試験に合格するしかなかった。そこで清作は、ドクトル渡部の会陽医院に書生として住まわせてもらい、徒弟教育的な実地による医術習得に励みつつ、寸暇を惜しんで勉強した。
明治29年春、清作の書生生活が3年に及び、医術開業試験のための具体的な準備にかかる必要を感じていた頃に出会ったのが、野口にとって生涯の恩人とも言える血脇守之助であった。明治26年に高山歯科医学院に入学した血脇は、28年に医術開業歯科試験に合格、9月からは学院の講師兼幹事を務めていた。学院の改革に尽力しつつ、夏季休暇中には会津若松に来て、渡部 鼎の会陽医院の筋向かいの旅館に一室を借りて出張診療を行っていたのである。診療を終えて、渡部院長と歓談していた血脇は、部屋の片隅で熱心に原書を読む清作の姿に驚き、上京の折には立ち寄るようにと励ました。この一言が、清作のその後を決める“天の声”となった。血脇26歳、清作19歳、ともに新時代にふさわしく、若く情熱にあふれた俊英であった。
|