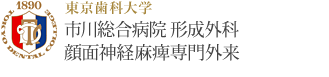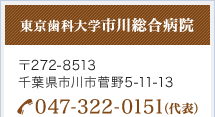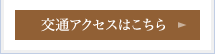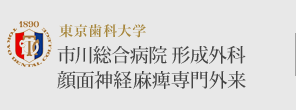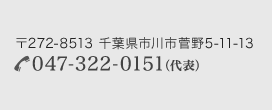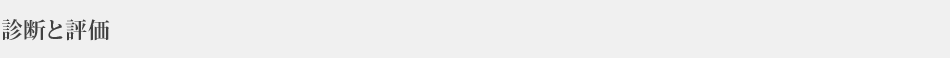
- TOP >>
- 診断と評価 >>
- 顔面神経麻痺の診断・評価についての概論
顔面神経麻痺の診断や評価としては、原因疾患や病態の診断、障害部位の診断、障害程度の診断や評価が必要です。
この中で障害程度の診断や評価は、麻痺の発症早期では重症度の診断や予後の診断に必要であり、その後は薬物治療や手術などによる麻痺の回復程度や治療効果の評価として必要です。
障害程度の診断・評価の方法としては、大きくは顔面運動評価法や電気生理学的検査(筋電図検査)が行われます。
顔面運動評価法としては、検査者が被検者を視診で判断する主観的評価法と、写真やビデオ画像などより計測やコンピュータ解析により行なう客観的評価法があります。
主観的評価法としては、部位別評価法の40点法(柳原法)、概括的評価法のHouse-Brackmann法、麻痺回復後の後遺症評価に重点をおいたSunnybrook法があります。
客観的評価法としては、マーカー法、モアレ法、レーザーレンジファインダ3次元形状計測法などがありますが、我々はビデオ画像からのコンピュータ解析によるoptical flow法を独自に開発して使用しています。
電気生理学的検査としては、針電極や表面電極を用いた各種の筋電図検査が主に使われています。